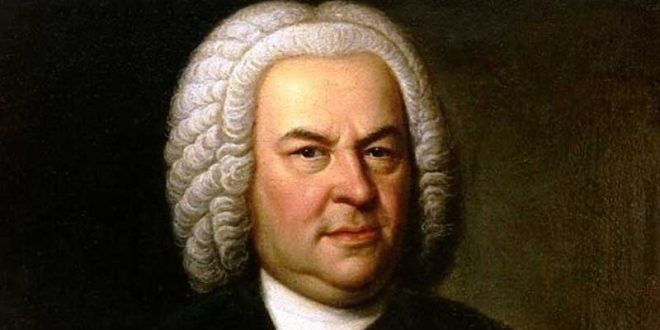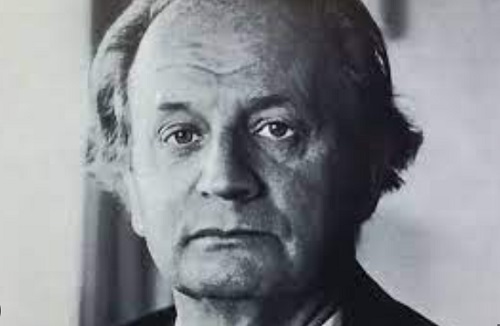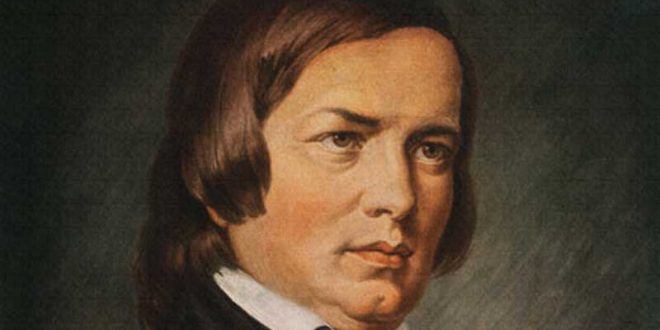美しい平均律のプレリュードを3回に分けて学ぶ第1回目は13小節まで見てみましょう。 ゆっくりのテンポで歌いながら揺れる子守唄のようなリズムを守りながら弾く曲です。 両手の声部の8分音符の旋律を交互に歌うイメージで。クレッシェンドは単に段々音量を大きくするのではなく気持ちの盛り上がりと捉えて音に向かって行くことを意識しましょう。 時には細かいタイミング(緑で表示)を自由に取って音を伸ばして弾いたり旋律を柔らかく。 旋律を膨らませて山を作りますがそれぞれの山の大きさの違いを+と-ではっきり意識して。 山の関係を考えて表現に繋げれば曲の構成や輪郭が分かりやすく更に旋律的になります。 フォルテやピアノなど単独の強弱記号よりも前後の強弱の関係を考えることが基本です。 アルペジオも歌って粘土をこねるような指先、鍵盤を引っ張る動きで旋律を歌いましょう。 6拍子より2拍子で考えて揺れるリズムを感じながらテンポを引きずらない事がネックです。 ペダルや強弱を忘れてリズムに集中するのも、歌う事に集中するのも其々良い練習です。 組み合わせた時には綺麗に歌いたい箇所もリズムが自由になり過ぎないようテンポを意識した良いバランスを探しましょう。次は装飾音、アルペジオ、トリルなども細かく見ます。 装飾音はいつもセンスよく長さや入れ方、タイミング、どの音を採用するか考えましょう。 例えば前打音は一音だけ前に弾くか、アルペジオ風にバラして弾くか、2音同時に弾いて不協和音を強調するか、色々な可能性を試して見ることで自分にとっての奏法が決まります。 装飾音を強調したり逆にあえて何も付けずに弾く選択もあるので吟味しながら進みます。 4段目のアルトの美しい旋律を強調するために手の方向は「10時」に向かって弾きます。 揺れるリズムの中に「小さな祈り」のような親密な空気が流れるように弾いてみましょう。
続きを見る »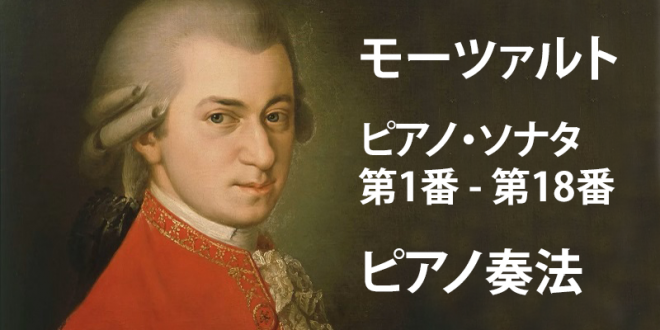
 ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール