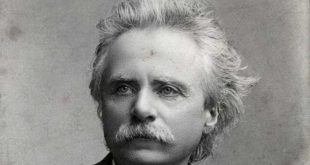今日はゆったりときれいなテーマで始まる2ページ目からのレッスンです。 オーケストラのように壮大に美しく歌うことをピアノでも再現しましょう。 アルペジオはハープのイメージを持ち左右の手で工夫して分担して弾きます。 アルペジオは音の分離を耳で確かめながらゆっくりペダルなしで練習します。 和音を耳で覚えて指で掴む為に同時に和音だけで弾いて指に記憶させます。 音を残しながら和音を繋げてレガート練習すると手が和音の位置を覚えます。 アルペジオは指より柔らかく手首をしならせるように使って弾きましょう。 クレッシェンドとデクレッシェンドを+と-で表し前の部分との関係を考えて。 メロディー=大、伴奏=小というバランスもとても大切です。 上向きの大きなクレッシェンドはたっぷり溜めて頂点のフォルテからピアノへ。 イタリアのオペラらしく表現は強くドラマチックに強弱を幅広く表しましょう。 旋律とともに伴奏も大きくなるとかなりのボリュームになるバランスを聞いて。 特に歌うように弾きたい時はタイミング=ルバートを意識しましょう。 ある所でたっぷり待ったらその後でその分を取り戻す様に音楽を先へ動かして。 きっかり拍子に合わせずに、毎回一拍目の前は少し待って=ルバート気味に。 アルペジオ強弱そしてルバートとはじめはそれぞれポイントを分けて練習も可。 最後に強弱、タイミング、バランス、アルペジオ全て組み合わせてペダルを使ってオーケストラのイメージを持って、少しハードルの高い豊かな音楽を気持ちよく弾きましょう。
続きを見る »レッスンビデオ
#214 マスカーニ 「間奏曲」(1)
イタリア人作曲家マスカーニのオペラ「カバレリア・ルスティカーナ」からお馴染みのメロディー「間奏曲(インテルメッツォ)」をピアノ編曲版で学びます。 オーケストラ曲のピアノ版ゆえ弾きにくく難しい箇所もゆっくり見て行きます。 ピアノには真似できない美しい弦楽合奏やオーボエ、オルガンが特徴的です。 カバレリア・ルスティカーナ=「田園風な騎士道」という意味を持ち、テーマが貴族社会から庶民へと移った頃の文芸作品に基づいて書かれました。 イタリア歌劇によくある恋のもつれの物語ですが音楽は素晴らしいです。 弦楽器らしい始まりのフレーズは止まらないよう16分音符で刻んで流れを意識。 音と音の間の繋がりを感じ、リズムをコントロールして良いタイミングで。 16分音符でリズムを刻む事で進んだり溜めたりも自然なタイミングを掴みます。 溜めて弾く2小節の1拍目は指のアタックだと美しくないので柔らかく押します。 手の動きの為には指使いを変えて。音の繋がりをよくしましょう。 左手の大きな和音はバスを前打音風に、あとの音はハーモニーの扱いに分けて。 5連符は一拍の中入るように練習してから→ルバート気味にゆっくり弾きます。 タイミングは意外に複雑です。溜めたらテンポを戻して、を繰り返します。 最後はテンポを緩めて丁寧に。和音は右で取れば左手の移動がスムーズです。 a-mollの13小節目フレーズは楽譜のアレンジではなく原曲のオーボエの旋律で。 曲を通して3拍目が美しく大切な拍になることが多いことを意識しましょう。 C-durに戻る瞬間からcresc.で歌って和音を割って弾く時は焦らずゆったり。 バランス、タイミング、強弱等余裕を持って自由に音楽を表現してみましょう。
続きを見る »#213 スクリャービン 前奏曲 op.11-4(2)
前回クレッシェンドからpに戻って又クレッシェンドする所を学びました。 2段目の最後の小節はアッチェレランドで速く→ゆっくりに戻ります。 1、2回目の短いスラーは波のように、3回目の長いフレーズは加速→遅く。 西欧では1拍目にアクセントが来るのに対しロシアは終わりの拍に向かいます。 スクリャービンもフレーズの最後、4拍目/6拍目に行き先を感じて弾きます。 4段目の途中、2段目と違うのは特徴的な突然の2拍分の休符です。 少しフェルマータ気味に長めに取ります。最後は裏にあった伴奏を表に出して。 クラシック音楽では連打は終わりが近い、死や運命など恐ろしさを表します。 よく聴くと連打は死神がドアをノックして最期を告げるような怖い音です。 左手の下降フレーズは嘆き。暗さの中に一瞬光が見えるがまたすぐ戻ります。 長い音が短くなって終わりに向けて段々落ち着きが無くならないように数えて。 左の最後のミは小さくても聴こえるように。最後はペダルをゆっくり上げます。 たくさんの事を学べるスクリャービンの名曲です。
続きを見る »#212 スクリャービン 前奏曲 op.11-4(1)
シンプルな小曲を美しく演奏する為にリズム/音色/バランスに集中します。 香り高いスクリャービンの独特な世界の表現を2回に分けレッスンします。 ゆっくり→加速→ゆっくり…と始めから、又一小節内でテンポが波打ます。 性格の異なる24曲のプレリュードの中でも第4番は暗い嘆き、悲しみに満ちたメロディーの中に光が差す曲です。この表現は簡単なようで難しいです。 テンポはレント、ゆっくり始まり加速しますが波のように柔らかいリズムで。 123456と数え方も伸び縮みするように自分のフィーリングを大切にします。 右和音、左旋律とも重さを乗せ、右の音色を添える和音のみ下から上に。 鋭い音色で違った響きを作ります。他の部分は全て重さを使いましょう。 歌いたい時には引っ張るタッチを使うと旋律的なショパン風になります。 深いダークな雰囲気の響きのためには重たいタッチを意識します。 sは歌って。右手のソプラノ、連打の和音、左手の3声の音楽と捉えます。 左バスの嘆きと寂しさの暗い旋律と右ソプラノの明るい光をバランスして。 左の旋律は歌うだけでなく強弱を考えて自由なルバートでタイミングよく。 2段目の1小節目は大きく(+)4小節目は弱く(−)強弱をコントロールします。 左フレーズの長いファ♯やド♯は保持して響かせ豊かな和音を導きましょう。 2回のクレッシェンドのあと、急にミ♯で一旦pに戻り再度クレッシェンド。 シンプルな曲ですが表現にこだわってより良い演奏へと磨きを掛けましょう。
続きを見る »#211 ドビュッシー ゴリウォーグのケークウォーク(3)
レガートとスタッカートが交互に出てくる中間部から見てみましょう。 Cedezはゆっくり、avec une grande emotionは気持ちを込めての意味。 スタッカートが多い曲の中、急に豊かなレガートの登場にびっくりします。 ワーグナーのオペラ「トリスタンとイゾルデ」から取ったテーマです。 解決しない和音の連結はトリスタンの和音と呼ばれ有名な和声進行です。 ドビュッシーはフレーズを拝借しユーモアを加えてアレンジしています。 軽いアメリカのジャズ風と、真面目なドイツ音楽の面白いミックスです。 ワーグナーは豊かにレガート、対するアチャカトゥーラ(短前打音)は鋭く。 内声のラーシ♭ーシの半音は悲し気なブルースから取ったフレーズです。 ユニゾンの最後の音は右手で取ると左手のバスの準備が楽になります。 音をおさえつつ鍵盤上で指を変えて右手上の動機を弾きやすいポジションで。 音楽は始めとほぼ同様でも工夫を凝らした和音の部分は大きく強弱変化させて。 ド♭シラソファ14321のあとミ♭は右手でオクターブを取って響きよく。 色々なスタイルが入った楽しい曲です。リズミカルに弾きましょう。
続きを見る »#210 ドビュッシー ゴリウォーグのケークウォーク(2)
今回は2ページ目を見てみましょう。 ピアノの中のクレッシェンドや、最後のffなど様々な強弱が出てきます。 左手の伴奏は54(3)-12、又は2の代わりに1の指で2音を取る事もできます。 cresc.して上の音は短く、ペダルも効果的に使いましょう。 左手はバスのみ+右手で和音を取ることで左の負担を軽減できます。 冒頭のテーマが出てきたら今回はアーティキュレーションを変えて。 下の段の変ト長調Un peu moins viteは「少し速さを減らして」という意味です。 少しテンポを落とし、左はテノールの旋律を出して右の単前打音は噛むようにとても短く弾きましょう。
続きを見る »#209 ドビュッシー ゴリウォーグのケークウォーク(1)
面白いタイトルの曲は子供の情景を彷彿とさせる子供の世界を表した曲集です。 ゴリウォーグは1895年作のF.Uptonによる絵本に登場する男の子の名前です。 ケークウォークはアフリカの民族舞踊発祥、アメリカで生まれたダンスです。 当時フランスではジャズ等の影響を受けた音楽が流行っていました。 軽快でシンプルなこの曲は凝った表現より小気味いいテンポをキープします。 スタッカートとアクセントを組合わせたマルカートは鋭く短く切りましょう。 1拍目の休符も意識的に鋭く感じ、1段目は出来るだけ大きな音で弾きます。 2段目の指使いは右手でファソをミシと一緒に弾けばずっと楽になります。 ただ3段目以降の跳躍に慣らしておきたい場合は楽譜通り左手で取ります。 とてもクリアに、とてもドライに、の表示に従いペダルは使わずに。 メロディーはppで音は切れても旋律的に。右手の重音は軽くルーズに叩いて。 強弱やアーティキュレーションを守って、わかりやすく少し大袈裟に表して。 fの音量の為には短くペダルを使って。テンポは急がずリズムをキープ。 コントラストを作って硬くならずダンスのリズムに乗って楽しく弾きましょう。
続きを見る »#208 グリーグ 抒情小品集「春に寄す」(4)
今日は3pページ目の下の段から曲の最後まで見てみましょう。 fのアクセントからdecしてpへ、そのあとcrescと細かい強弱を意識します。 左手の裏拍のアクセントとcresc、decなど強弱やタイミングなど3小節の中の細かい豊かな指示を曲の気分を感じながら、こだわりをもって表現しましょう。 無意識に弾くのではなく左の伴奏も和声を感じながら旋律的にレガートで。 ffとcrescの後盛り上がるかと思えば急にpになり曲は幻想的に終わります。 2段目2小節から和声はh→G→E D→fisと3度の関係で変化しています。 リストなどロマン派に見られる3度変化の和声進行は幻想的な味わいです。 ハリーポッターの不思議な感じの音楽でも同じような進行が聴こえます。 エンディングのジャズ風な面白い和音を経由して最後の和音に着きます。 少し戻り4拍目フェルマータは休むように時間を取って急がず、ffでは大きくcrescした後たっぷり待って期待させ→意外な展開の和音は絶妙なタイミングで。 雰囲気を感じること、クライマックスを作る事が大切です。 最後近くの左アルペジオは5321指で時間かけて登りペダルはゆっくり離して。 次の和音はラレを25に変えレだけ残しドに繋ぎやすいポジションへ移って。 レ♯レドをレガートにするためペダル踏み替えるタイミングにも注意します。 少し戻って長いアルペジオはワンペダルでdimとritしながら消えて行きます。 次のffの和音はトッカータのように急に荒々しく→とても優しくなります。 曲の最後の部分はグリーグがテンポ感がない世界を描いています。 色々な演奏を聴いてこだわって自分の曲のイメージを磨いていきましょう。
続きを見る »#207 グリーグ 抒情小品集「春に寄す」(3)
前回からの続きで2ページ目の下の段から見てみましょう。 fffの部分から始めのテーマに戻る所はたっぷり待って落ち着いてから。 大きな音量からpへの切り替わりはに心身脱力できる時間を取ります。 寒いノルウェーに春がやってきた喜びを感じましょう。 オクターブはインパクトを和らげるために軽く手首を回してバラします。 右手伴奏の重音連打は控えめな音量で鍵盤を上まで離さず半分の位置から。 左手アルペジオはゆっくり→速く→ゆっくりのルバートで膨らまします。 強弱よりルバートを優先すれば弾き易く、音楽も柔らかく流れ出します。 オクターブで遅くなったらそのあと少し速くしてテンポを戻しましょう。 音楽が重くならないようルバートは遅く→速くを組合せて波を作ります。 手の向きは時計に見立てて上の音を出すには2時、下の音は10時の方向に向かえば 気持ちよく脱力できて立体的な音のバランスが得られます。ワンフレーズ繰り返し止まらないで弾く「ループ練習」でタッチ、テンポ、強弱、タイミング、脱力、まず一つに集中し、次の段階で2つ以上の要素を組み合わせていきます。 繰り返しながら情景や香り、ストーリーなど曲のイメージにも触れましょう。 溜めて弾くタイミング、音色の変化も意識してグリーグの世界を描きましょう。
続きを見る »#206 グリーグ 抒情小品集「春に寄す」(2)
前回からの続きで1ページの下の段から2ページ目を見てみましょう。 明るくなった音楽が一気に影って段々クライマックスに近づいて行きます。 右の連打は明るい響きから→上半身の体重をかけるように重さを乗せて。 左右とも旋律は指を独立させずにスライドできる指使いでレガートに。 poco a poco strettoは少しづつ速く、更にテンポを上げて行きましょう。 フレーズをレガートで弾くことに慣れていればテンポアップも容易にできます。 ラファソミは右5453 左1213がスムーズです。和音連打の伴奏は最低限の音で鍵盤を上まで離さずにハーフキーで音楽が盛り上がっても旋律とのバランスを保ちます。 3拍子から4拍子に変わる=ヘミオラの緊張感も意識しましょう。 力強いオクターブのメロディーの箇所も伴奏は独立した連打でなく震える様に。 動きを持って拍を感じて、ffだけは伴奏も重いタッチで拍感の違いを意識。 音のバランスは三段三様の強弱で。旋律は鳴らし和音の連打は膨らみを作って。 タイミングは連打を4グループに分け、最初と最後は遅く、その間の音は速く。 強弱、タイミング、タッチ、動きを1つずつ別々に取り上げて練習します。 長調に戻る前のc#は音量が減って行くのを聴き違和感なくテーマに繋いで。 頭で弾くより耳を使って響きを聴きながら音楽を感じて楽しみましょう。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール