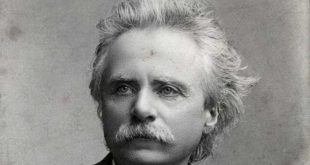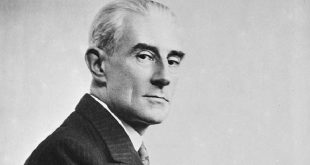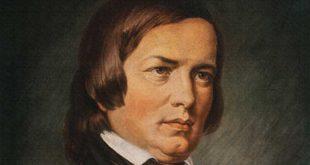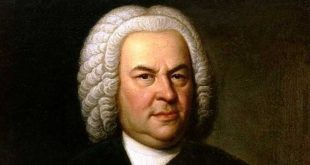今日は3pページ目の下の段から曲の最後まで見てみましょう。 fのアクセントからdecしてpへ、そのあとcrescと細かい強弱を意識します。 左手の裏拍のアクセントとcresc、decなど強弱やタイミングなど3小節の中の細かい豊かな指示を曲の気分を感じながら、こだわりをもって表現しましょう。 無意識に弾くのではなく左の伴奏も和声を感じながら旋律的にレガートで。 ffとcrescの後盛り上がるかと思えば急にpになり曲は幻想的に終わります。 2段目2小節から和声はh→G→E D→fisと3度の関係で変化しています。 リストなどロマン派に見られる3度変化の和声進行は幻想的な味わいです。 ハリーポッターの不思議な感じの音楽でも同じような進行が聴こえます。 エンディングのジャズ風な面白い和音を経由して最後の和音に着きます。 少し戻り4拍目フェルマータは休むように時間を取って急がず、ffでは大きくcrescした後たっぷり待って期待させ→意外な展開の和音は絶妙なタイミングで。 雰囲気を感じること、クライマックスを作る事が大切です。 最後近くの左アルペジオは5321指で時間かけて登りペダルはゆっくり離して。 次の和音はラレを25に変えレだけ残しドに繋ぎやすいポジションへ移って。 レ♯レドをレガートにするためペダル踏み替えるタイミングにも注意します。 少し戻って長いアルペジオはワンペダルでdimとritしながら消えて行きます。 次のffの和音はトッカータのように急に荒々しく→とても優しくなります。 曲の最後の部分はグリーグがテンポ感がない世界を描いています。 色々な演奏を聴いてこだわって自分の曲のイメージを磨いていきましょう。
続きを見る »レッスンビデオ
#207 グリーグ 抒情小品集「春に寄す」(3)
前回からの続きで2ページ目の下の段から見てみましょう。 fffの部分から始めのテーマに戻る所はたっぷり待って落ち着いてから。 大きな音量からpへの切り替わりはに心身脱力できる時間を取ります。 寒いノルウェーに春がやってきた喜びを感じましょう。 オクターブはインパクトを和らげるために軽く手首を回してバラします。 右手伴奏の重音連打は控えめな音量で鍵盤を上まで離さず半分の位置から。 左手アルペジオはゆっくり→速く→ゆっくりのルバートで膨らまします。 強弱よりルバートを優先すれば弾き易く、音楽も柔らかく流れ出します。 オクターブで遅くなったらそのあと少し速くしてテンポを戻しましょう。 音楽が重くならないようルバートは遅く→速くを組合せて波を作ります。 手の向きは時計に見立てて上の音を出すには2時、下の音は10時の方向に向かえば 気持ちよく脱力できて立体的な音のバランスが得られます。ワンフレーズ繰り返し止まらないで弾く「ループ練習」でタッチ、テンポ、強弱、タイミング、脱力、まず一つに集中し、次の段階で2つ以上の要素を組み合わせていきます。 繰り返しながら情景や香り、ストーリーなど曲のイメージにも触れましょう。 溜めて弾くタイミング、音色の変化も意識してグリーグの世界を描きましょう。
続きを見る »#206 グリーグ 抒情小品集「春に寄す」(2)
前回からの続きで1ページの下の段から2ページ目を見てみましょう。 明るくなった音楽が一気に影って段々クライマックスに近づいて行きます。 右の連打は明るい響きから→上半身の体重をかけるように重さを乗せて。 左右とも旋律は指を独立させずにスライドできる指使いでレガートに。 poco a poco strettoは少しづつ速く、更にテンポを上げて行きましょう。 フレーズをレガートで弾くことに慣れていればテンポアップも容易にできます。 ラファソミは右5453 左1213がスムーズです。和音連打の伴奏は最低限の音で鍵盤を上まで離さずにハーフキーで音楽が盛り上がっても旋律とのバランスを保ちます。 3拍子から4拍子に変わる=ヘミオラの緊張感も意識しましょう。 力強いオクターブのメロディーの箇所も伴奏は独立した連打でなく震える様に。 動きを持って拍を感じて、ffだけは伴奏も重いタッチで拍感の違いを意識。 音のバランスは三段三様の強弱で。旋律は鳴らし和音の連打は膨らみを作って。 タイミングは連打を4グループに分け、最初と最後は遅く、その間の音は速く。 強弱、タイミング、タッチ、動きを1つずつ別々に取り上げて練習します。 長調に戻る前のc#は音量が減って行くのを聴き違和感なくテーマに繋いで。 頭で弾くより耳を使って響きを聴きながら音楽を感じて楽しみましょう。
続きを見る »#205 グリーグ 抒情小品集「春に寄す」(1)
グリーグの美しい小曲「春に寄す」を4回で学ぶ1回目は1ページ目を見てみます。 左手の脱力、右手の三和音の連打とのバランス、左右2:3のタイミング等も見ます。
続きを見る »#204 ラヴェル ハイドンの名によるメヌエット(3)
ラヴェルのメヌエットを勉強する最終回は2ページ3段目以降から見てみましょう。 3段目不思議な和音が出てきて4段目でテーマが戻りシンプルな展開で終わります。
続きを見る »#203 ラヴェル ハイドンの名によるメヌエット(2)
ラヴェルの小品を弾く2回目のレッスンです。前回の続きからみてみましょう。 HAYDNからとったシ-ラ-レ-レ-ソの5音がソ–レ–レ–ラ–シと後ろ向きで登場。 テーマを後向きや逆さに挿入するのはバロック期のフーガによくある技法です。
続きを見る »#202 ラヴェル ハイドンの名によるメヌエット(1)
ラヴェルの素敵な小品を3回に分けて見て行きます。 今日は始めの3-4段目の曲の作り方、和声、強弱や表現、雰囲気をみてみます。 ハイドン没後100年に当る1909年、音楽雑誌の企画で6人の作曲家に曲を依頼。 HAYDNの名前にちなみシ-ラ-レ-レ-ソの5音から成る6つの作品が生まれました。
続きを見る »#201 シューマン 子供のためのアルバム「冬」(2)
今日は曲の後半です。まずは3段目の強弱は出だしと比べて大きく始まります。 矢印を参考に先に進む、ルバート、ritなどリズムをパンパンパンと取ります。 機械的な練習は音楽にとって最も大切なフィーリングを壊すので要注意です。 テンポは遅くてもフレーズ感を失わないように気をつけましょう。先週の続きでアルトの音を連打しながら強弱は考えず良いタイミング、リズムを探します。 次は歌い方、強弱です。crescを山の大きさで考えてそこへ向かったり降りたり。 アルペジオの後は小さく始まりcresc-decの波を何度か作りながらpに導きます。 4段目のテーマが戻る所はppで冒頭に比べゆっくり幻想的な静かなトーンで。 最後のシューマンらしい複雑な声部はそれぞれ単独で弾いて動きを確かめます。 慣れたらソプラノとテノール、ソプラノとアルトなど2声を重ねて弾きましょう。 無理して弾くより色々な声部をよく聴きながら美しい音に気付くのが大切です。 自分の音を客観的に聴きながら自然なタイミングを感じ取りましょう。
続きを見る »#200 シューマン 子供のためのアルバム「冬」(1)
ゆっくりした寂しく悲しい雰囲気の小さな曲です。 リズムの感じ方と拍感、旋律的に歌う事とその2つを組み合わせる練習をします。 初めの小さなフレーズは質問→答→質問→最後の答と4つの動機で出来ています。 このフレーズをリズムが機械的に硬くならないよう注意して自然にルバートで。 16分音符の感じ方は数字の8を横にした形を描く様に切らずに塗るイメージで。 パンパンパンと口でリズムを取るのもルバートで指もそれに合わせて弾きます。 右のアルト又は左のテノールで拍を取るように16分音符の連打で弾いてみます。 溜めて弾きたい時に16分音符はritで弾き、その後テンポを戻すのを繰り返しながら自由なリズムの感覚を掴みましょう。慣れたら16分音符を頭の中で感じます。 どの曲にも応用ができるリズムの練習方法です。次はフレーズを歌いましょう。 音に向かって弾く感覚が大切です。音のcrescより気持ちの盛り上がりに集中。 「音を大事に弾く」捉え方も良いです。同じ表現より強弱は色々変化させます。 次のステップはリズムと歌い方の融合です。腕や肩、上半身も音楽に沿わせて。 ppも2回目はウナコルダにしたり変化のある表現を意識しましょう。 リズムはいきなり曲に飛び込まずに始まる前に∞の形を描いてそれに乗ります。 ソプラノはもちろん重要ですが時にはアルトを強調したり左のテノールを少しだけ聞かせたり、表現を楽しみながら弾いてみましょう。
続きを見る »#199 バッハ 前奏曲 cis-moll BWV849(3)
バッハ 平均律 第1巻 第4番 プレリュード cis-moll BWV849 ③ 3回目の今回は2ページ目の4段目以降〜最後まで見て曲を完成させましょう。 29小節でドラマティックに終わってコーダで静かになりますが→もう一回クライマックスが来て→テンポの押し引きがあり→最後に小さく盛り上がり終ります。 エンディングは色々とこだわることができますが、いったん29小節に戻ります。 pの音量から始まって段々膨らませて。a↘︎f♯の大きな音程は劇的な意味です。 バロックの世界で大きな音程は宗教的な痛み、悲しみ、大変な事を表します。 ピアノで2つの音を弾く事は簡単ですが大変そうに歌いながら音程を味わって。 左手は落ち着いて。テンポを揺らしながらエンディングに導いて行きます。 6度など音程大の箇所は少し、33小節のf♯↗︎aの大きな音程はたっぷり溜めて。 テンポにこだわりながら、歌う事と上手くバランスしながら弾きましょう。 35-36小節はスラーのついたアーティキュレーションや前打音も見逃さずに。 37小節は縦のライン=和声もよく聴いて。最後はritで和音はアルペジオも可。 オルガンの響き「アーメン」のようにも聴こえます。リズムを失わないように歌います。テンポ感と歌、2つの要素のバランスを大切に美しく弾きましょう。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール