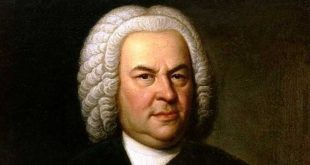バッハ平均律のプレリュードを学ぶ2曲目は13番です。 平均律クラヴィーア曲集の後半の始めの曲になります。 前半の最後、12番が暗いfーmollから少し光が差した所で終わりました。 13番は新しい始まり、春、新しい命を感じられる生き生きと明るい曲です。 奏法のビデオのD -durプレリュードと同じ部分、また違いもあります。 123、123 と16分音符を一拍目に強拍を感じてベースを作りましょう。 次の段階では3拍を一拍で取って、1-2-3-4と1小節を4拍子で感じて。 拍の強さは強-弱-中-次(アウフタクト)と、奏法ビデオでも学びました。 でも表現の段階では必ずしも当てはまるわけでなく弱拍が強拍になる事も。 2-3、7-8小節など場所により3拍目が強拍になり面白い感じになります。 始めは3拍目にアクセントをつけて、次は強調した3拍目同士をレガートで。 シラソファミレドの下降音階を繋いで行く要領で。次はラシドレミと上昇。 このように3拍目を繋ぎながら滑らかに長いフレーズを作って行きます。 ペダルは3つ目の音の上で踏み替え、少し勢いを感じ命、明るさを表して。 野原で子羊が遊んでいるようなイメージで表現しましょう。 トリルは上から3つ目又は4つ目の音のあたりまで。 左も旋律的に4音、4音、4音、6音をワンフレーズで感じましょう。 fis-durはバロックにはない調性で更に黒鍵のgis ais cis disに転調します。 5音あわせるとペンタトニックスケールです。12小節のトリルは短めに。 生き生きと明るいイメージのトーンで演奏してみましょう。
続きを見る »レッスンビデオ
#229 バッハ 前奏曲 no.9 (2)
今月はバッハ平均律のプレリュードを2曲学びます。今回は9番の後半です。 レガートを中心に見ていきましょう。厳密に言えば音を重ねて弾く事です。 一つの音を次の音を出した後も伸ばします。ミーソーシと3つ重ねても可。 指でレガートを繋げます。1指だけ残して和声的に弾くのも良いです。 レガート感とは実際に音が繋がっていなくてもレガートに感じる事です。 離れている2音の間は音程を大切に弾くイメージで。 始めからレガートで練習しましょう。指スライドでもレガートを作れます。 +と-で表した所は-をレガートで。バラして弾くとレガートを作り易いです。 場所によりスタッカートで軽くあっさりさせてバランスを保ちましょう。 2p目もレガートに集中します。アルトの声部を良く聴いて。 左バスは進む→待つを繰返して波を作って。16分音符の右より左がリード。 16分音符は手首を小幅で上下させて。技術的に聴こえない様左レガートで。 a-durのは明るく軽い調子で。スタッカートも用いれば生き生きとした印象。 V→IでなくVIに行くのが偽終止。最後はアルトからテノールへ繋いで。 最後の和音はアルペジオでゆっくりと。e-durの優しさとa-durの華やかさ、途中に現れるfis-moll の性質の違いも味わいながら弾いてみましょう。
続きを見る »#228 バッハ 前奏曲 no.9 (1)
今月はバッハ平均律のプレリュードを2曲学びます。今回は9番前半です。 3度で上がる主題はクレッシェンド感じ、バスも同じように従って。 クレッシェンド、デクレッシェンドはプラスとマイナスで感じます。 この曲の明るい音は下から上に立ち上がるタッチで表しましょう。 逆に手首を下げて弾くと落ち着いた真面目なトーンになります。 フレーズがクレッシェンドに向かう時は手首を上げるように。 旋律が下がる時のレガートは下にスライド、手前にひっぱって。 右手のため息のモチーフも同じように2音を一度引っ張る動きの中で。 指で歌う事も大切です。右は歌に慣れていますが左手のバスも旋律的に。 片手で練習して音と音の間を歌う気持ちで伸ばします。 左にテノールの声部が出る部分はバスとのポリフォニーを聴いて。 長い音は特に歌って豊かな響きをキープしながら2声の行方を追って。 両声部を別々に弾いたり、実際声に出して歌ってみたりと旋律的に。 和音は時にはフランス語で壊す、ばらすという意味のスティルブリゼで。 バロックではスタッカートなどアーティキュレーションは弾き手次第。 1p目後半で短調が聴こえて音楽が濃くなりがちな場所はスタッカートで。 スタッカートを使うと明るい印象に。2p目の主題の表現の変化にも。 クレッシェンドの表示は音楽の減衰防止のために表示しています。 調は今どの調にいるか意識する為に念のため書き込みます。 トリルはドレドが弾きやすいですがバロックは普通レドレドと上から。 静止して上から弾くと硬いので左手から出る身体の動きの流れで。 4小節の装飾はドレミレミレミレミレ〜と下から引っ掛けて長めに。 左手クレッシェンドで入り長い音はよく歌って存在感を意識します。 強弱はプラスマイナスで急なアクセントがつかないように注意して。 フレーズ最後でゆっくりになったら次はテンポを戻して。 ドラマティックな音は感情を表すよりよく和声の緊張感を聴いて。 ペダルは浅く踏み、離す方に意識を持って。ペダルなしの練習も良いです。
続きを見る »#227 チャイコフスキー「四季」より1月 (4)
チャイコフスキーの四季「1月」の最終回は最後まで見て行きます。 5ページは第1-2回の復習で、6ページ2段目〜の新しい部分を見ます。 2段目から波を作り3小節目が山。右のフレーズを左が追いかけます。 右ラのフォルテのオクターブと左のカノンは絶妙なバランスで。 和音がどの音が加わることによりどの瞬間で変化するか良く聞きます。 チャイコフスキーのマジックを感じてファソラーミは毎回音量減らして。 曲のコーダ部分の仕上げこだわりましょう。 弦楽器やホルン、オーケストラの楽器の音色を意識して表情豊かに。 ある声部や特定の音を出したりしながら色々なバランスを試します。 テンポも自由に感じブレーキかけたりritにすると同時に拍感も大切に。 アルペジオ部分はルバートする前に一度8分音符のリズムで感じてから。 ペダルも後から加えますが、3拍目で上げてラだけ残るペダリングで。 最後の3つの音は「月の光」の様な光る音色を下から上の奏法で出して。 ritで3つ目は長めに自然に。ペダルをゆっくりupして最後の一音が消えるまで雰囲気をキープして音楽を作ることを意識しましょう。
続きを見る »#226 チャイコフスキー「四季」より1月 (3)
チャイコフスキーの四季「1月」の中間部を見て行きましょう。 曲が幻想的な雰囲気に変化し、音楽が感情的に展開する部分です。 3p目、中間部の始めのモチーフはよく歌い指は554543でレガートで。 拍感を感じながら。16分音符は流れないように指先しっかり優雅な動き。 水など動きのあるものをイメージしましょう。 ヘミオラを感じるより3拍子で取って、音楽は3拍目に向かいます。 西欧の音楽は1拍目が強く、ロシア音楽ではフレーズ終りの拍が強いです。 メロディーと伴奏のバランスをよく聞いて軽く重さを感じないように。 左手から右手に送るように回し、左右の繋がり、流れを感じて軽く。 手首は柔らかく、独立した指ではなく腕の動きで16分音符を捉えて。 技術的に音楽を理解すれば楽に弾くことができます。 4p目〜もロシア人演奏家のアイディアを借りてアルペジオをつけて柔軟に。 音楽は先に行ったり止めたり自由なリズムで。 メロディー(f)とハーモニー(p)のバランス大切に。 16分音符の伴奏はルバートを波のように感じて弾きましょう。 休符を感じながら弾くタイミングをつかめると良いです。呼吸も意識。 2段目の最後は3拍目を意識。ヘミオラのリズムを改めて確認します。 テーマに戻る前は思い切ってritしてみましょう。
続きを見る »#225 チャイコフスキー「四季」より1月 (2)
チャイコフスキーの四季「1月」の1p目最後から見て行きましょう。 右手の優しいレガートは3拍目を大切に、1拍目の8分音符を長めに感じて。 左はレガート+スタッカートし易い5132321の指使いで長い音にアクセント。 アクセントに向かってアッチェレランドするタイミングで弾くとより自然に。 バランス的に右手を少し出し左は練習時アクセント強めに→後で減らして。 down -up(大-小)の動きは身体も柔らかく一緒について行きましょう。 つま先で歩くバレエのような可愛らしい所です。ペダルは離す瞬間を意識。 down(大)-up(小)は一つの動きの中、upは弾く事をほとんど意識しないで。 downは上から手を落とす空中で音を掴み指で覚えると技術的に安定します。 この動きで長いcrescとdecはスムーズにp-mp-mf-f-mf-mp-pを意識します。 最後はペダルを入れて長いクライマックスのフレーズを描きましょう。 down-upを長く-短く取ることで余裕を持ってリズムをコントロールして。 急がずにテンポを自由にルバートで感じるのがコツです。 曲はゆったり始まり→中間は勢いが出て→盛上がりますが気持は焦らずに。 いつも強弱とテンポをコントロールできる冷静さを保てば演奏も安心です。 クライマックスの練習では身体も心も脱力を意識しましょう。
続きを見る »#224 チャイコフスキー「四季」より1月
チャイコフスキーの四季から素敵な「1月」を4回に分けて見て行きます。 12曲それぞれに小さな詩がついていますが1月はプーシキンによるソネット。 厳しい冬だからこそ暖かさ=幸せが感じられるように弾きましょう。 暖かい雰囲気のために柔らかい音色を作る「なでる」タッチを使います。 曲のイメージやトーン、「言葉」をつかむことが大切です。 ロシア音楽では流れがフレーズの最後に向かって行くことを意識します。 例えば2小節目のeーcにを大事に。強弱より気持を盛り上げて行く感覚で。 頭で理解して弾くより感覚的に捉えられると良いでしょう。 レガートが多い中のノンレガート、スラーの間も小さなブレスを感じ明るく。 フレーズ始めのf音などは長めに取れば温かさが表現できます。 休符は一瞬ペダルを離して。細かく使って踏み替えを意識しましょう。 3段目poco piu forteで少し大きく、次は対照的にp、3回目はルバートで。 4段目は次回見ますが、ゆっくりと速くを組合わせて動きを作り出します。 モーツァルトと言えばオペラ。チャイコフスキーと言えばバレエです。 バレエの中の動きや表現、舞踏の要素で出来た音楽と理解しましょう。
続きを見る »#223 C.P.E.バッハ 「ロンド」(3)
エンディングは左手がドラマチックに展開します。 アルペジオと右手のターンのような旋律を経てテーマに戻ります。 個性が強めの左の不協和音は勇気を持って強調しましょう。 引っ張って弾く可愛らしいデクレッシェンドと重さを乗せて弾く劇的なクレッシェンドの対比を感じて。重さを感じながら弾く場所は音を切るようにひとつづつ意識。 35指から→23指でトリル→15へ。最後はdimの方向です。 バロック時代の作品らしく最後の和音はアルペジオで終わるのも可能です。 シンプルで分かりやすい表現の曲です。テーマが戻る所は思い出すようなロマンティックなトーンで弾いてみましょう。
続きを見る »#222 C.P.E.バッハ 「ロンド」(2)
CPEバッハ作曲h-mollソナタ最終楽章のビューロー編曲版です。 バロックの響きの中に多くの装飾音など古典風の要素が聴こえます。 b moll→Gフォルテ→e少し音量を減らして和声の変化を表します。 短い動機を音を変えて進行するセクエンツ(反復進行)が聞こえます。 左手の和音も5度進行でポップスなどにもよく使われる手法です。 emollのp(-)でテンポが落ちているので次のフレーズでテンポup。 トリルは2-3指が簡単。ritして→a tempoでテーマに戻ります。 左手のフレーズは<>が大切。右メロディーはきれいに歌って。 左手の不協和音の悲しい気分を味わって、次のstringendoに向かって。 accelerandoはテンポupですがここは音楽の緊張感に集中します。 クライマックスのフォルテは手に重さを乗せて弾きましょう。
続きを見る »#221 C.P.E.バッハ 「ロンド」(1)
バッハ息子のひとり、CPEバッハ作曲h-mollソナタ最終楽章を19Cに入り ドイツのビューローが編曲した「ロンド」を見ていきます。 シンプルな原曲の素敵なピアノ用アレンジです。 アンダンテは遅くなりすぎずに程よく 流れるテンポをキープしましょう。 カンタービレでよく歌って、フレーズ最後の音に向かって表情豊かに。 左の和音は半音階のバスの上に成り立った美しい和音を聴きましょう。 下降半音階の悲しい雰囲気を味わって。長いフレーズを4つに分けます。 左手テノールのメロディーは強調して。トリルは長めに段々ゆっくり。 3段目は各フレーズの終わりはゆっくり。左手も旋律的に表情豊かに。 3つ目のフレーズは可愛らしさが厳しさに変わります。 4段目はmfからcrescで歌って、最後のトリルはritして終わります。 歌うトーンは引張るタッチでシンプルな表現を愉しみながら弾きましょう。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール