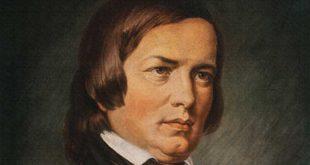Louis
#246 シューマン 森の情景「寂しい花」(3)
今日は2ページ目の前半見ていきます。 前回の最後、感動する場所でテンポを落としました。 今回はそこからcrescしながら元のテンポに戻していきます。 声部バランスを考えながらペダルも使いテンポは少し押し引き。 ペダルは濁らないように音符ごとによく踏み替えましょう。 高いラ音は少し溜めてルバート。タイミングで大切さを表して。 2段目は新しい部分です。テンポを上げてmfでよく歌います。 アルトがソプラノの形を真似る間、ソプラノは独立した旋律です。 ソ-ドと大きな音程を持つテノールの旋律にも注目しましょう。 右手はソプラノを出すためにアルペジオで弾きます。 3段目はシンプルな曲想。右手は声部を分けず一つの和音として。 Cresc は小さくフレーズを膨らますイメージです。 crescと共に落ちてきたテンポを少し戻し、美しさをppで表して。 自然なエンディングに向かうようなテンポと強弱で。 ゆっくり時間を掛けてこだわっていい演奏を目指しましょう。
続きを見る »#245 シューマン 森の情景「寂しい花」(2)
前回からの続き、1ページ目の下の2段を見て行きます。 ゆっくりのペースで自分が好きな演奏を探して行きましょう。 前回はソプラノとアルトの旋律、バランスに着目しました。 ここからは左手の2つの声部を聴くのが大切になります。 テノールのレ-ミ-レ、バスのソ-ファ-ミ-ド-レ等意識します。 縦の和音を取るより、横に2声の旋律を辿って行きましょう。 次は右を合わせて3声を色々なバランスで試してみましょう。 場所によってどの声部を出すか、懐中電灯でどこを照らすか考えます。 次は上の2声部もよく聴いて美しさに感動しながらに味わいましょう。 バスとテノールの掛け合いも聴きながら。バスのシ♭は深く強調して。 4声のパートをそれぞれ分かってバランスよく歌い上げましょう。 タイミングは矢印の通り→先へ動いて、又は←溜めてrit気味に。 このテーマの終わりはアダージョのように大きくritしましょう。 次の4小節は曲中最も美しい場所です。上2声の掛け合い味わって。 バランス的にはソプラノを歌ってアルトは軽く影のように薄く。 ここは寂しい花=幻想的なイメージを持って弾くことが大切です。 出だしのテーマのシンプルさに比べ陰影がついて深みがあります。 演奏することを恐れたり抑え込まずに冒険のように試したり楽しんで弾きましょう。
続きを見る »オンライン講座 (9) 2025-06-10
奏法 クレメンティ ソナチネ Op.36-3 第1楽章 (1)
#244 シューマン 森の情景「寂しい花」(1)
シンプルに見えて複雑な声部、和音を表現するのが難しい曲です。 短く技術的には易しいですが4回に分けてゆっくり丁寧に学んで行きます。 右手は2声:まずテーマがアルトに登場し2小節目でソプラノが加わります。 同時に2声を聴きましょう。3-4小節は逆転してソプラノがテーマです。 そのテーマの終わりの4小節にまたアルトでテーマが入ってきます。 縦に取ると不協和音が目立つのでなるべく声部=横のライン考えましょう。 音楽を理解することが大切です。アルトとソプラノ掛け合いをよく聴いて。 例えばアルト60%,ソプラノ40%など音量バランスをコントロールします。 ソプラノを強調したい時は手を右に傾け、アルトを出したい時は左に回して。 音量コントロールは少し大袈裟に練習します。まず50%づつからずらして。 縦で考えるのは不協和音が強すぎて音楽が分かりにくくなるので注意します。 左手の伴奏は始めはシンプルですが4段目に動きが出て複雑になります。 強弱は、よく歌うところ(S)、デクレッシェンド、クレッシェンドを 3段目はソプラノのファ-ミ-レ-ラ-ド-シを出して。主張したいなら少し溜めて。 表現するにはタイミングと強弱によるコントラストが大切です。 自分の好みで声部のコントロールを楽しみながら弾けると良いでしょう。
続きを見る »オンライン講座 (8) 2025-05-29
奏法 クレメンティ ソナチネ Op.36-2 第3楽章 (2)
10 (2) シューマン 「子供の情景」 2025-05-24
#243 ショパン ノクターン第8番 (4)
今月はショパンのノクターン8番を学ぶ最終回です。 クライマックスの後から最後までを見て行きます。 f→ppへコントラストを作り長い装飾的なパッセージは自由に。 練習ではまずはゆっくり左右を合わせて慣れたら自由に動かします。 左右の合わせやすい音を楽譜上に線で繋いでいます。 合わせ方は均等に4づつで合わせるより3-4-4-4-4-5だと弾き易いです。 付点の練習はLsss(長短短短)、sssL(短短短長)など変化させましょう。 手を脱力して手首から柔らかく回して弾きます。 旋律はソプラノですが3度下のアルトの声部の変化をよく聞きます。 con forzaの3:2は情熱的に。速くならないようテンポはコントロール。 始めにも出てきた嘆きの音型の後、また感情が盛り上がります。 ppのコーダのショパンらしい溜息はマジカルな美しさです。 幻想的な半音階は左1指のテノールを強調させて。強弱は<>で。 「雨だれ」や涙がこぼれる情景を思って。 ソプラノとアルトの絡みは2人の会話のように。最後は2声仲良く。 6度の上昇のタイミングはまず2-3-2 2-3-2で取り、その内自由に。 消えていくように。6度のフレーズ後ペダルは一度切って休符を意識。 バッハの影響でもある多声的な濃さを味わって弾いてみましょう。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール