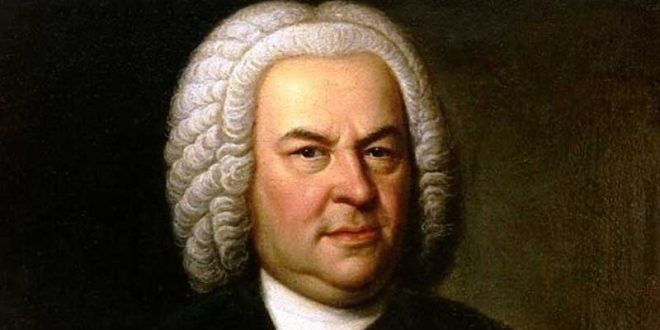フィンランドの美しい作品の最後の2ページを見て行きましょう。 難しさを忘れて美しく弾くことに集中できると良いです。 左手の伴奏の指は521321 521421と波を意識しながら静かに。 右の旋律を想像しながら強弱とタイミングもまずは左手だけ弾きます。 右は3-125-2-125-3-125-3-124…和音の真ん中の音3と2よく聴いて。 メロディは上の音です。内声も理解して指でも覚える事が大切です。 指でパターンを掴むと弾き易くなります。トリルは遠慮せずritとdim。 次は左最初の6つの音を聴いて。初めの和音はアルペジオでもOK。 クレッシェンドで勢いがつかないようにテンポをキープしながら。 1,2拍目mf→3,4拍目pp→次の2拍は+→次の2拍はー→crescで。 前と違う和音の色を意識。右手は歌い1回目と2回目は表情を変えて。 4段目の左の指使いは1pと同様521125が最適。ペダル踏み替えて。 テーマが戻って来る所ソドは思い出すように幻想的に風に乗って。 遠くからの所はpで弾きます。pでも右旋律は歌うトーンで。 1pはプラスだった3小節目と異なりそのままpをキープします。 強弱を変えずにタイミングだけ自由にすると薄い色彩感で効果的に。 ソラソファミファソも時間を取ってゆっくり弾きます。 pの後の最後の方の和音は深い響きを出して印象的に表現します。 ピアノの鍵盤に深く沈み込んで上と下の和音を響かせてみましょう。
続きを見る »
 ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール