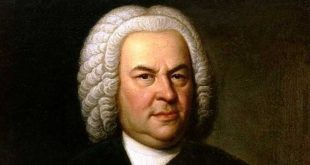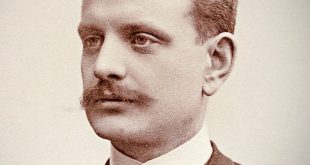Louis
3-2 バッハ 「インヴェンション」2025-12-20
#270 シベリウス「樅の木」(3)
シベリウス「樅の木」の3回目は2ページ目を見ていきましょう。 深い暗い音→前のdolceと同じ旋律→即興的な部分が出てきます。 下3段の速い動きは少し技巧的。上の2段は表現を意識します。 前のワルツ部分からの繋がりを感じ、暗い深い音は手首下げて。 前のdolceで明るく弾いた旋律を、今度は落ち着いた悲しい音色で。 暗い音を出すためには鍵盤を下へ下げるように柔らかいアクセント。 内声の旋律シ-ラ/ソ−ファを意識して。休符でペダルをup。 右手波型は2つの動きを合わせて。まず左から右回し→左へ戻る。 もう1つは手前へ引っ張って→奥へ戻す動きで。指も活発に。 指を振り下すように2回タップしてから弾く練習しましょう。 鍵盤を離すことや指を動かす事を意識しながら。軽やかに。 左手は強く出します。右の32分8つの音は入口は遅く、出口は速く。 上の音は少し強調します。どの位の力が必要か考えながら練習します。 ペダルはよく踏み替えて等、盛り沢山ですが段々弾き易くなるはず。 ペダルを離す時に手前へ指を引っ張り、ペダルを指の動きに合わせて。 risolutoは断定的な強さでリード。テンポはバスで1、2と取ります。 4段目は盛り上がりを一度pに戻し一瞬待って改めてクレッシェンド。 波を2つ作るイメージです。指を上げて手首を柔らかく左右に回して。 内声シーラーレードの部分が聴こえるバランスを作りましょう。
続きを見る »3-1 バッハ 「インヴェンション」2025-12-13
#269 シベリウス「樅の木」(2)
全体の雰囲気〜細かい所も学びました。豊かな表現に満ちた小曲です。 冒頭の即興的なパッセージが悲しいワルツに変わるのをよく聞いて。 3段目のダークな色調から明るい方向へ音色が変化して行きます。 暗い色は脱力して腕の重さを鍵盤に乗せて、深く下へ入るように。 そこから少し上へ意識して、dolceでは下から上に立ち上がるタッチ。 ドビュッシーの月の光のような明るい音色を作ることができます。 ここはルバートのリズムの中で少し先に行くようにテンポupして。 フレーズの終わりでまたテンポを戻すのを2回繰り返します。 次の部分ワルツのリズムになっても同様に。テーマはアダージョです。 dolceは左手の親指を出して。和音を時計の2時の方向押します。 小さいニュアンス程度で十分な立体感が生まれます。 休符を聴かせるためにペダルを離すとテンポが少し変化して素敵です。 最後の段、右手は親指のメロディーと外側の指の伴奏は自然に回して。 右伴奏を一つずつ下げて弾くと音が重く大きく鳴り過ぎます。 左の和音は右の旋律を迂回する動きでバランス聴きながらテンポup。 下の段の強弱は< >で。この曲は自由に感じるのが最も大切です。 音色を変化させルバートを気持ちよく感じながら弾いてみましょう。
続きを見る »オンライン講座 2025-12-09
奏法 クレメンティ ソナチネ Op.36-6 第1楽章 (2)
#268 シベリウス「樅の木」(1)
先月に引き続きフィンランドの作曲家の作品を学びます。 「樅(もみ)の木」はシベリウス作曲のこの季節に相応しい素敵な曲です。 「感傷的なワルツ」とも表すことができ、即興的にゆったり流れます。 冒頭から雰囲気を掴む事が大切。右はワルツ、左は2拍子です。 strettoはバロック音楽の言葉で、フーガのテーマが次々現れます。 アラルガンドは段々遅くなりながらクレッシェンド、の意味。 練習ではテンポと強弱を別々に。6カウントが5拍に変わるのを意識。 ソプラノを出してレガートで弾いてみましょう。2つの音を繋いで。 音が多い時はその中から主要な音を選んで出しましょう。 ペダルは表示通り2回だけでは濁るので和音が変わる毎に踏み替えて。 このオープニングの部分は即興のイメージで自由に弾きましょう。 プレリュード風または即興曲にタイミングにこだわってみます。 3拍子の右手は親指がメロディーラインです。他の音は伴奏で軽く。 メロディーになれるためあまり強弱を気にせずfで出すことに集中します。 右手は片手で重いメロディーと軽い伴奏に差をつけながら練習しましょう。 ニュアンスをつけるにはアクセント、クレッシェンド等用いてみます。 1と2と3と…と実際にリズムを口に出して数えながら。 ペダル離してブレスを入れて。アルペジオは急がずに勢いを付けずに。 ルバートをコントロールしてイメージ通りにテンポを伸び縮みさせて。 自由過ぎにならないよう、リズムを刻む方向で。 2段目の5小節めの旋律ファ♯は左であとは右で引き継ぎます。 強弱を大きなグループで+と−で考えてコントラストを作りましょう。 +の部分は手にかかる重みを増やすイメージで、逆に−は軽いタッチで。 色々な表現を味わいながら哀しい雰囲気を作って弾いてみましょう。
続きを見る »2-3 バッハ 「インヴェンション」2025-11-29
#267 カスキ「夜の海辺にて」 (4)
フィンランドの美しい作品の最後の2ページを見て行きましょう。 難しさを忘れて美しく弾くことに集中できると良いです。 左手の伴奏の指は521321 521421と波を意識しながら静かに。 右の旋律を想像しながら強弱とタイミングもまずは左手だけ弾きます。 右は3-125-2-125-3-125-3-124…和音の真ん中の音3と2よく聴いて。 メロディは上の音です。内声も理解して指でも覚える事が大切です。 指でパターンを掴むと弾き易くなります。トリルは遠慮せずritとdim。 次は左最初の6つの音を聴いて。初めの和音はアルペジオでもOK。 クレッシェンドで勢いがつかないようにテンポをキープしながら。 1,2拍目mf→3,4拍目pp→次の2拍は+→次の2拍はー→crescで。 前と違う和音の色を意識。右手は歌い1回目と2回目は表情を変えて。 4段目の左の指使いは1pと同様521125が最適。ペダル踏み替えて。 テーマが戻って来る所ソドは思い出すように幻想的に風に乗って。 遠くからの所はpで弾きます。pでも右旋律は歌うトーンで。 1pはプラスだった3小節目と異なりそのままpをキープします。 強弱を変えずにタイミングだけ自由にすると薄い色彩感で効果的に。 ソラソファミファソも時間を取ってゆっくり弾きます。 pの後の最後の方の和音は深い響きを出して印象的に表現します。 ピアノの鍵盤に深く沈み込んで上と下の和音を響かせてみましょう。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール