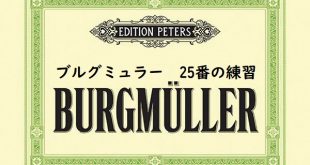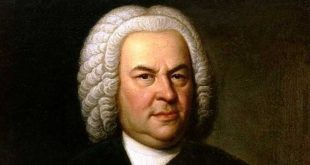1pの後半から2pのクライマックスを見て行きます。 まず2p目から、左はミタカ-ミタカ-チョーフのリズム。 f~p~cresc.など強弱も合わせて片手で練習します。 右手は2拍をノンレガートで旋律を拍に合わせて。 アルペジオは急がずに下の音をすぐに弾きすぐ離すと良いです。 慣れたらペダルと強弱を入れましょう。 次は両手で、また最初に戻りペダルを外して重さを乗せて。 左右のバランスを考えて左と右のアルトを減らして旋律に集中。 左右の手が近づく時は引き易く上下のポジションを考えます。 次は強弱を出して同じテンポでペダルを入れて。 ミスしやすい所は早目に対処する事が大切です。 最後に音色のバランスやタイミングを調整しましょう。 全体に重さを乗せて弾きます。次は前の部分から繋げます。 1p下の2段は引っ張る奏法でここはノンレガートで。 レガートの多い中で時々現れるノンレガートが素敵です。 リズム、拍を指でも感じながらノンレガートを強調します。 フレーズの終わりまで少し濁ってもペダルを踏み続けて。 ソシだけ残しペダルをup。響きの変わる瞬間を聴きましょう。 ブラームスのespressivoは少し時間を掛けて弾くとよいです。 左右ともよく歌って勇気を持ってテンポを柔軟にコントロールします。
続きを見る »#277 ブラームス 間奏曲 Op.116-4 (2)
1pの後半から2pのクライマックスを見て行きます。 まず2p目から、左はミタカ-ミタカ-チョーフのリズム。 f~p~cresc.など強弱も合わせて片手で練習します。 右手は2拍をノンレガートで旋…
#276 ブラームス 間奏曲 Op.116-4 (1)
美しい小品の歌い方、タッチ、強弱、音色、リズム等を学びます。 4回に分けて、今回は1ページ目、前半の3段を見てみましょう。 アダージョの少し不気味なテーマの後に優しく幻想的なモチーフ。 深くダー…
最新投稿
奏法 ブルグミュラー「25番の練習曲」No.2a
#276 ブラームス 間奏曲 Op.116-4 (1)
美しい小品の歌い方、タッチ、強弱、音色、リズム等を学びます。 4回に分けて、今回は1ページ目、前半の3段を見てみましょう。 アダージョの少し不気味なテーマの後に優しく幻想的なモチーフ。 深くダークな響きから優しく明るい音楽に変化します。 盛り上がりの前のテンションを感じられる部分です。 左はアウフタクトからpでも重さを乗せてしっかり腕から押して。 対照的に右dolceは優しく鍵盤を撫でて弾きましょう。 2段目右手ドレミファはペダルを踏んだまま一つづつノンレガート。 ソミドラはレガートです。その後の左も同じノンレガートのタッチ。 深い音は前屈、軽い音は身体を後へ引き腕にかかる重みを制限して。 音楽を身体の動きで覚えられると良いでしょう。 遅いテンポでリズミカルにキープするために左右の3:2を明解に。 2つ=チョーフ、3つ=ミタカとリズムを取ると簡単で正確です。 ペダル無しのドライな状態で自分の拍で練習し自然な拍感を得て。 ペダルは踏み替えのタイミングをよく聞いて時には音を混ぜて。 ダーク→優しく→明るく→幻想的など雰囲気の変化を味わいながら弾きましょう。
続きを見る »#275 バッハ シンフォニア No.5&7 (4)
前回は用語、分析や曲の構成を学びました。今回は弾き方を見ます。 音色や表現など、音楽的な部分に集中していきます。 左手のバスは旋律的に歌いながら。右アルトが入る瞬間を聞いて。 codetta、間奏、結句、テーマ、対旋律も耳で確認しながら進みます。 不協和の7度の他、5度、4度など音程も和声もよく聞きながら。 短3度が重なってできている減7の和音の緊張感もアルペジオで確認。 曲はe-mollから始まって→h-mollに着きました。間奏の転調は劇的。 旋律的に弾くことが大切ですが段々縦にも和声を聞いていきましょう。 提示部や間奏の和声と旋律をよく聞いて片手ずつ練習しましょう。 3つ目の柱=リズムも重要です。メトロノームでなく自然なリズム感。 音楽をリズミカルに感じて。リズムの強弱と流れ、タイミングが大切。 123456とカウントしながら自然な流れとタイミングを掴んで。 第2提示部の始まりで硬くならないように。ペダルは外します。 弾きながらメロディー・和声・リズムの3つに集中しましょう。 特に間奏は美しい和声を耳で追って。 ソプラノの16分音符をアルトが引き継ぐ(答唱の)タイミング注意。 左を伴奏と考えて小さく、右のテーマは美しく歌いましょう。 ソプラノとアルト2声の音程を和音のように捉えます。 左手も同様にバランスをよく下のバスを強調するなどよく聴いて。 右手だけに集中せず4音の短いバスのフレーズもメロディックに。 旋律的に、和声を聴いて、特にタイミングも重要ポイントです。 長い音を伸びているように膨らみを感じることも大切。 提示部はしっかりした形を意識し、一方間奏は即興の要素を感じて。 間奏は少しテンポを緩めに自由に感じても良いでしょう。 それぞれの声部や分析した内容を意識しながら弾きます。 構成を理解すると譜読みし易くなりますが分析だけに捉われずに。 リズムや音も自由にバッハ作品を表現しましょう。
続きを見る »奏法 ブルグミュラー「25番の練習曲」No.1b
#274 バッハ シンフォニア No.5&7 (3)
シンフォニアをフーガの簡単版と捉えて分析してみます。 今回は用語、分析の仕方や曲の構成などを説明していきます。 ソナタ形式(提示,展開,再現部)と異なり幾つかの提示部で構成されます。 提示部と提示部の間に間奏が挟まっているのが特徴です。 1〜8小節が第1提示部、9〜13間奏、14〜20が第2提示部と続きます。 提示部と間奏の組み合わせを一つの大きなフレーズと考えられます。 提示部は英語でexposition、間奏はepisodeや移行部とも呼ばれます。 提示部のテーマは「主題(主唱、subjectなど)」と呼ばれsopに登場。 3声のフーガは通常Sop/Alt/Basそれぞれ主題の後→間奏となります。 Sop主題の後Altの主題「答唱(answer)」は通常5度上(4度下)で始まり、 BasはSopと同じ音の主題。これが第一提示部で次に間奏に入ります。 主題の下、別の声部の旋律「対位旋律(対唱)」は曲中に繰り返されます。 テーマとテーマの間の小さな間奏は「結句(codetta)」と呼ばれます。 右手の下にすぐ対位旋律、altの主題の時にsopは伴奏、そのあとが結句。 Basのテーマの上Altで対位旋律。このように何度も出てきます。 第一提示部のあとは→間奏エピソードが始まります。 この曲の第二提示部はAltの主題で始まり→Sopが答唱→Bas主題。 20小節から間奏→終止、とここまでが前半の構成の分析です。 主題と答唱を強調して弾くことも可能ですがバランスをよく考えながら。 主題より対位旋律を出して弾く方がきれいな場合も多くあります。 分析は曲の理解に繋がります。和声進行など曲のパターンを判れば新しい曲の譜読みも容易になります。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール